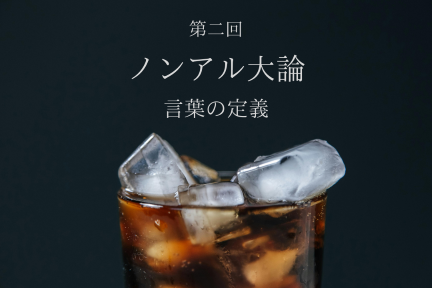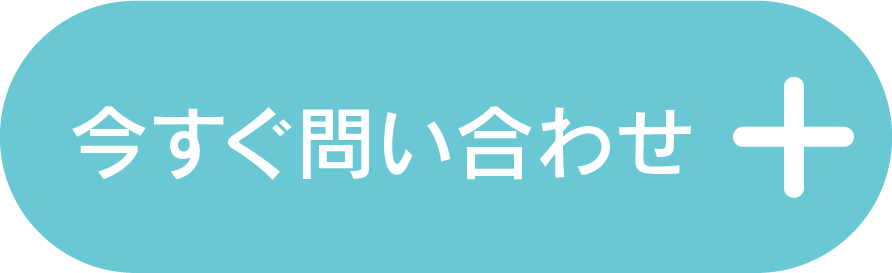「ノンアルコール飲料」というと、あなたはどんなイメージを持ちますか?
当然、「アルコールの含まれていない飲み物」じゃないの?
と思うかもしれません。
しかし、実は調べてみるとそう単純ではないようで…。
今回はノンアルコール飲料の言葉の定義について、少し掘り下げてまとめてみたいと思います。
- 辞書にはなんと書いてある?
- 法律上、表示基準に基づく定義
- 消費者目線での注意
1.辞書にはなんと書いてある?
まず、辞書やWebで調べたときに、どのように説明がされているかを調べてみましょう。
三省堂編修所 編『見やすいカタカナ新語辞典 第5版』
ノンアルコール飲料
①アルコール分を含まない飲料。いわゆるソフト-ドリンク。▶︎ノン-アルコールドリンクとも。
②アルコール分を含まないか、わずかに含む(1%未満である)アルコール風飲料。ビール風飲料(ビールテースト飲料)など。
三省堂編修所 編『見やすい現代国語辞典 第二版』
ノンアルコール
飲み物で、アルコールを含まないもの。「-ビール」[nonalcoholicから]
Wikipedia
上記を含み、アルコール飲料以外の飲料(アルコール飲料の基準は後述の通り、国や地域で異なる。)。
アルコール分を含まない、としか記述のない辞書もあるようですが、
微量にアルコールを含んでいるものも指すという風に説明がされています。
『見やすいカタカナ新語辞典 第5版』には具体的に「1%未満である」とされていましたが、これは何を基準にしているのでしょうか?
2.法律上、表示基準に基づく定義
結論、この「1%未満」というのは酒税法を基準にしています。
ただし、ここでは「アルコール飲料か、そうでないか」という法律上の区分になっているということです。
現行の日本法には、「ノンアルコール飲料」という名称そのものを一義的に定義した法律はありません。
法的な位置づけは、下記のようなレイヤーで成立しています。
- 酒税法で「酒類かどうか」を判定
- 食品衛生法で「清涼飲料水」として衛生規格を適用
- 食品表示法・健康増進法・景品表示法で表示ルールを適用
- 国税庁告示・業界の自主基準で「ノンアルコール飲料」の実務的定義や注意表示を補完
- 海外の基準
酒税法では2条で「酒類」を「アルコール分1度以上の飲料」と定義しています。
そして、食品衛生法の下位通知・規格基準で、「清涼飲料水」を「乳酸菌飲料、乳および乳製品を除く、酒精分1容量パーセント未満を含有する飲料」と定義しています。
ですので、ノンアルコール飲料(0.00%)はもちろん、0.5%等を含む微量アルコール飲料も、原則としてこの「清涼飲料水」に含まれる。ということになります。
そして、「清涼飲料水」扱いになると酒類ではなくて食品として扱われるのだそうです。
管轄が違うんですね。
酒類は酒税法管轄の表示義務(国税庁)、
食品は食品表示法管轄の表示義務(消費者庁+厚労省+農水省)
に則って表示・販売するように定められているそうです。
3.消費者目線での注意
体質やシチュエーションで、まったくアルコールを飲めない人にとって、これは気をつけなければなりません。
「ノンアルだと思って飲んだのに、ちょっとアルコール入ってた!」
なんていうことが起きてもおかしくありません。
厳密にアルコールを排除しなければならない状況がどれぐらい存在するかは分かりませんが、
アルコールを全く受け付けない体質の方や、業務にあたってアルコール厳禁のパイロットや職業運転士の方は十分に注意する必要がありそうです。
景品表示法では、「ノンアルコール飲料」の表示について、
– 実際にはアルコールを含む飲料に「ノンアルコール」等と表示すると、消費者が「全くアルコールを含まない」と誤認するおそれがある–
として、表示の適正化を事業者団体に要請といった経緯を公表しているとのことです。
とはいえ、パッケージをパッと見ただけではわからない商品が混在しているのは事実。
ご自身で飲むときはシチュエーションによって選択できるように。
お客様に提供する立場の飲食店の方々は、なるべく「0.00%」表示の商品を探すか、
確実にアルコール分が入っていない製造工程だと確認できたものをラインナップするようにしましょう。
海外の基準はどうなっているのか気になりますね。
次回は日本以外の国のノンアルコール事情を探ってみたいと思います。