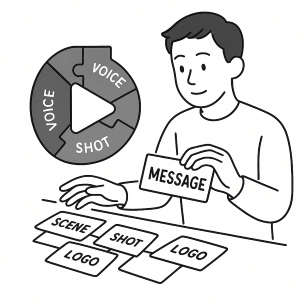前回の記事では、制作費用の話に絡めて「動画の目的」と「誰に向けたものか」を明確にすることで、
企画の出発点が定まるという話をしました。
しかし、実際に企画を立てようとすると次にぶつかるのが、「あれもこれも伝えたい」という問題です。たとえば、採用動画をつくるときに
・理念も伝えたい
・福利厚生も紹介したい
・社風の良さも出したい
・社員の声も入れたい
となって、結果的に「要素は多いけれど印象が薄い」動画になってしまうことがあります。
情報が多い=伝わるではありません。
むしろ、「伝えたいことを1つに絞る」ことで、動画の力は何倍にもなります。
今回は、そんな動画の“伝える軸”をどう決めるかについて掘り下げていきます。

1. なぜ「ひとつのメッセージ」が必要なのか?
● 情報過多の時代に「覚えられる動画」は強い
SNSやYouTubeの動画があふれる今、「記憶に残る」コンテンツは一貫したメッセージを持っています。
逆に、複数の要素を詰め込みすぎた動画は、視聴者の頭に何も残らないまま終わってしまいます。
● 覚えられる=共有されやすい
たとえば、印象に残る動画の多くは、**“ひとことで語れるメッセージ”**を持っています。
Apple(広告):「Think different」
→ 製品の機能ではなく“思想”を伝えることで、ブランドを確立。
サイボウズ(採用動画):「100人100通りの働き方」
→ 多様な社員のライフスタイルを見せ、「自分にもフィットするかも」と感じさせる設計。
(※YouTubeで「サイボウズ 採用」などで視聴可能)
ヤッホーブルーイング(会社紹介):「ビールが好きすぎる会社」
→ 商品紹介よりも“社員の熱量”が伝わるユニークな演出で印象に残る。
LIFULL(ブランディング):「しなきゃ、なんてない。」
→ 企業メッセージがそのまま動画の軸になっており、生活者視点とブランド理念が一致。
こうした事例の共通点は、動画の中に「一貫した視点や価値観」があることです。
そして、それを“覚えやすい言葉”や“ストーリー”で表現しているからこそ、視聴後に人に話したくなる、保存したくなる動画になっています。

2. とはいえ「言いたいことが多い」は本当に悪なのか?
「伝えたいことが多すぎて、まとまらない」
動画制作の現場でよく聞く悩みです。
前段と矛盾するように思えますが、伝えたいことが多い=悪い企画ではありません。
それは、むしろ企業としての強みや魅力がしっかりある証拠です。
問題なのは、「全部を均等に詰め込もうとすること」。
● 印象は“総量”ではなく“集中”で決まる
人の記憶に残るのは「伝えられた情報量」ではなく、
その情報がどういう“印象”を残したかです。
たとえば以下のような整理をしてみてください:
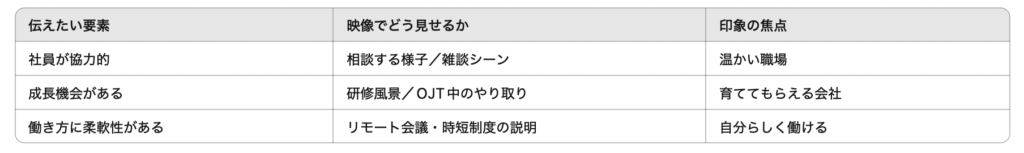
→ この3つの内容はすべて伝えても構いませんが、
動画全体の印象は「温かい会社」に集中させる、という方針をもつこと。
それがメッセージ設計です。
● 情報は削らず、「演出の序列」をつける
複数要素があるときは、「主メッセージに向かって補足情報を寄せていく」ような構成が理想です。
すべてを平等に語るのではなく、映像の順番、尺、トーンによって“意味の重さ”を調整します。

3. メッセージは“言葉”ではなく“演出”で決まる
「キャッチコピーを考えるのがメッセージ設計」
そう思われがちですが、動画の場合は少し違います。
動画のメッセージは、“何をどう見せるか”で決まるからです。
● 演出が変われば、同じ素材も違うメッセージになる
たとえば社員インタビュー素材が1本あったとします。
- BGMがピアノ:あたたかさ、誠実さ
- BGMが電子音:スタイリッシュ、スピード感
- 編集テンポがゆったり:ナチュラル、親近感
- 編集テンポが速い:活気、プロフェッショナルさ
さらに、構成順も重要です。
1.冒頭に「迷っていたが入社してよかった」と語る
→ エモーショナルな企業ストーリーになる
2.後半に同じ言葉を配置
→ それまでの映像全体が“裏付け”として機能する
このように、「何を伝えるか」より、「どう伝えるか」の設計こそがメッセージになります。
● 「1分で伝わる動画」=「1分間すべてが“同じ空気”をまとっている」
視聴者は、動画の隅々まで情報を拾ってくれるわけではありません。
でも、全体を通して一貫したトーンや世界観があれば、
言葉にしにくい“感覚”としてのメッセージが伝わります。
“言いたいことが多い”状態からスタートしても、
動画の印象設計=メッセージ設計という視点があれば、
効果的な1本に仕上げることができます。

4. まとめ
まとめましょう。
動画制作における「メッセージ設計」とは、キャッチコピーを決めることではありません。
それは、動画全体を通じて“どんな印象を残したいか”を定め、
その印象に向けて構成・演出すべてを調整する行為です。
伝えたいことが多くても構いません。
むしろ多い方が、素材としては豊かです。
ただし、それらを“均等に見せる”のではなく、中心に据えるメッセージを決めて、他の要素はその補強に徹する。
それが、観た人の心に残る動画をつくるための基本姿勢です。
そしてそのメッセージは、文字ではなく映像・音・順番・間といった視覚と感覚の総合演出によってつくり上げられます。
一貫した空気をまとった動画は、1分でも人の心を動かします。
だからこそ、企画段階で「何を伝えるか」だけでなく、“どう感じさせたいか”という視点を持つことが、動画の完成度を大きく左右するのです。
こうした掘り下げの部分を丁寧に行えるかは、動画制作を依頼する外注先との関係性も重要です。
「撮って終わり」ではなく、継続的に信頼できるパートナー選びができると、
動画コンテンツの資産価値もより高まっていくことでしょう。